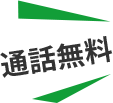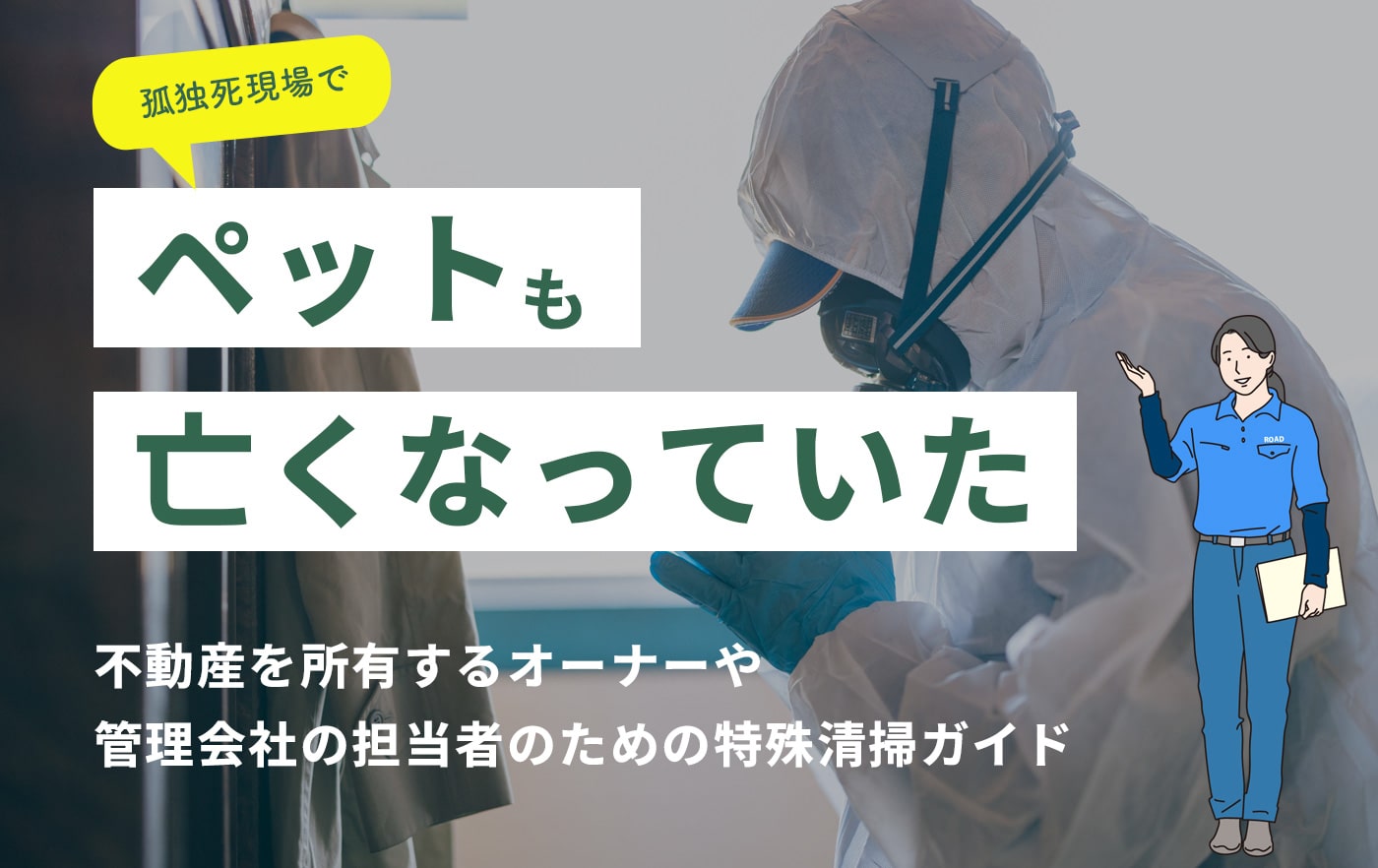
「入居者が孤独死で見つかり、借主が飼っていたペットも亡くなっていたようです。」——管理会社からの連絡を受けた瞬間、状況は見えないまま、不安だけが時間とともに大きくなっているのではないでしょうか。孤独死という現実に向き合うだけでも重いのに、そこに犬や猫がいたとなれば、その不安はなおさらです。
孤独死の発見が遅れると、腐敗したご遺体から流れ出す血液などの体液が広がます。その上に、ペットの糞尿なども複雑に混ざり合い、強い臭気が部屋じゅうに広がり、とても一般の清掃では落とすことができない状態になっていることがほとんどです。
それでも、どうか落ち着いてください。焦らずに順番を踏めば大丈夫です。正しい初動と、特殊清掃の専門家の手が入れば、この部屋は必ず元の表情を取り戻します。次の入居者を迎え入れられる状態まできちんと戻すことはできます。
この記事では、突然の事態に立ち尽くしているであろうアパートを所有するオーナー、また入居者が高齢で孤独死のリスクを感じているオーナーのために、「まず何をすべきか」から「ペットがいる現場特有のリスク」、清掃の流れ、原状回復までの道筋を、現場をいくつも見てきた目線でまとめました。
一度に理解しようとしなくても大丈夫です。必要なことを、ひとつずつ順番に整理していきましょう。
目次
まずは落ち着いて状況確認を。「ペットありの孤独死」で大家が最初に行うべき初動対応
孤独死現場では、急いで動き判断を誤れば、本来必要のない費用まで積み上がってしまうこともあります。まず意識したいのは、たった三つ。
「入室しないこと」「状況を整理すること」「関係機関と連携すること」。特に「入室しないこと」は重要です。警察や管理会社の確認が終わるまでは、扉の向こうに踏み込まないことが、結果的に復旧までの道のりを一番短くします。
焦りを少し脇に置き、指示を静かに待つこと。それが最初にできる、もっとも確かな一歩です。
警察の現場検証が終わるまで入室は厳禁
警察の検証が終わる前に部屋へ入ってしまうと、意図せず現場を乱してしまうことがあります。体液や汚れを気づかずに踏み、その足で部屋の中を歩き回り、汚染を広げてしまう場合があります。
そうなると本来の汚れの位置が分かりにくくなり、どこまで浸透しているのかを改めて調査する必要が出てきます。結果として、清掃にかかる時間も費用も大きくなります。
また、孤独死の現場には体液や腐敗ガス、害虫が広がっているだけでなく、目に見えない細菌やウイルスなどの病原体が存在し感染症のリスクが高くなりますが、これらは一般的な防護では身を守りきれません。ペットがいた場合は糞尿などがあり、さらに汚れがひどくなります。
だからこそ、最初に守るべきことはただひとつ——触れないこと。警察と管理会社からの連絡を待ち、鍵が正式に戻ってきてから専門業者へ依頼する。この流れを崩さないだけで、余計なトラブルも二次的な汚染も防げます。
ペットの対応について
残念ながらペットも亡くなっていた場合は、人の遺体とは異なる手順が必要になります。自治体の動物遺骸の扱いに従うか、特殊清掃業者に収容と搬送を依頼することになります。
小さな遺骸でも腐敗は早く、体液が思いがけない範囲に染み込み、強い臭気の原因になります。どちらのケースでも、オーナー自身が触れたり判断を急いだりすると、後々の費用が大きくなることがあります。無理をせず、専門家に任せること。それが、最も確実な選択です。
一方で、もしペットが生きている場合は、まず保護が最優先です。ペットが驚いて部屋を走り回り、これ以上汚れを広げてしまわないよう、優しく保護するようにしましょう。
ずっと部屋に閉じ込められていたからか、すぐにでも外に出ようとするペットもいるようです。不用意にドアを開けたままにして逃げてしまわないように注意しましょう。
連帯保証人・相続人への連絡と保険の確認
孤独死が起きたとき、面倒でも向き合うべきは事務的な連絡です。管理会社と状況を共有し、連帯保証人や相続人へ丁寧に伝えていきます。誰がどこまで費用を負担するのかは契約によって異なるため、早い段階で確認しておくことで後の行き違いを防げます。
また、火災保険や孤独死保険に加入している場合、特殊清掃や原状回復の一部が補償されることもあります。とくにペットがいた現場では汚れや臭気が深刻化しやすく、解体や強い脱臭工程が必要になり、オーナーの負担が大きくなるケースも少なくありません。
だからこそ、保険の確認は初動の中でも重要度の高い作業です。費用の見通しがつくだけで、復旧までの段取りがはっきりと形を取り始めます。
ペットがいた孤独死現場は「通常の孤独死現場」とどこが違うのか
ペットがいた孤独死の部屋では、ご遺体から漏れた体液に加え、ペットの遺骸や糞尿が混ざり、臭いも汚れも深くなりがちです。害虫が増え、体液や糞尿などが床や壁の内部まで達することもあります。その分、通常より工程が増えがちです。まずは、その前提を知っておくことが大切です。
ご遺体からの体液とペット遺骸・糞尿による複合的な悪臭
孤独死の現場では、ご遺体の腐敗による体液やガスが強い臭いを生みます。そこにペットがいた場合、動物の遺骸や糞尿が重なり、臭いはさらに複雑になります。
特に暑い夏場では、わずかな時間でも腐敗臭が床や壁の内部にまで入り込み、部屋の空気そのものが変わってしまうことがあります。
この混ざり合った臭いは、市販の消臭剤では消せません。特殊な薬剤やオゾンを使った工程が必要になります。それが、この種類の現場が難しいと言われる理由のひとつです。
走り回ったことによる体液の拡散と床・壁への浸透
飼い主が亡くなったあと、ペットが不安や空腹のまま部屋を動き回ることがあります。その足で体液や排泄物を踏んでしまうと、汚れは床や壁へと広がり、思っている以上に深いところまで入り込んでいきます。
床材や巾木、壁紙だけではなく、その下のボードやコンクリートにまで達することもあります。外側だけを見るときれいに見えても、内部には腐敗菌や臭いの成分が残っていることが多く、表面の掃除では限界があります。その結果、解体が必要な範囲が広がり、時間も費用も大きくなります。
オーナーとして大切なのは、「どこまで汚れが入り込んでいるのか」を正確に見極められる業者を選ぶことです。そこが、復旧の精度を決める部分になります。
害虫(ウジ・ハエ)の発生リスクが格段に高まる理由
遺体が腐敗すると、ウジやハエはすぐに集まってきます。そこにペットの遺骸が加わると、有機物が増え、害虫の広がりは一段と早くなります。
夏場や換気の悪い部屋では、ほんの数日で大量のハエが生まれ、室内を飛び回るだけでなく、隣の部屋にまで届いてしまうことがあります。ウジが床下や壁の内側に入り込むと、あとからすべてを取り除くのは難しく、時間が経ってから臭いや衛生トラブルが再び出てくることもあります。
対処には、殺虫剤を撒くだけでは足りません。原因になっている汚れを取り除き、建材の奥に残った菌まで処理する必要があります。こうした作業には工程がいくつもあり、専門の業者が欠かせません。
復旧費用が高額化しやすい理由
ペットがいた現場では、汚れの広がり方が違います。解体が必要になる範囲が増え、害虫の処理や強い脱臭工程も欠かせません。作業にかかる時間も薬剤の量も、通常の孤独死より大きくなりがちです。
その分、費用が上がりやすい——ただ、それを知っておくだけでも、次の判断がぶれなくなります。
ペット死骸処理という追加工程が発生する
ペットの遺骸は、自治体によって扱いが異なり、人の遺体とはまったく別の手続きが必要になります。特殊清掃の業者が収容し、腐敗液や汚れが残った場所をまとめて処理していくため、どうしても工程は増えていきます。
小さな動物でも腐敗の進み方は早く、体液が広く染み込むことがあるため、対応が遅れるほど臭いや汚れは大きくなります。その結果、清掃だけでなく、脱臭や解体が必要になる範囲も広がり、費用に直結していきます。
特殊清掃は「早く動くこと」が何よりの基本ですが、それはペットが亡くなっていた場合はなおさらです。清掃や消臭、除菌のスキルやノウハウを持っていることが前提ですが、その上でできるだけ早い対応ができる業者を選ぶことが、負担を抑える近道にもなります。
汚染除去から再募集まで。原状回復に向けた特殊清掃の具体的な工程
ペットがいた孤独死の部屋を元の姿に戻すには、除菌から汚れた物の撤去、害虫駆除、消臭・脱臭、必要に応じた解体、そして原状回復の工事まで、いくつもの工程を重ねる必要があります。
その全体像を知っておくだけで、漠然とした不安は少し形を持ち始めます。どこから始まり、どこまで行けば再び募集できる状態になるのか——その道筋をつかむことが、オーナーにとって大きな助けになります。
除菌作業
孤独死の現場で最初に行われるのは、部屋全体の除菌です。ご遺体の腐敗が進むと、体液だけでなく細菌やウイルス、腐敗に伴って発生する菌が部屋中に広がります。壁や床、家具の表面だけではなく、空気中にも漂っているため、汚れた物の撤去に入る前に、まず空間を整える必要があります。
ここで使われるのは、市販の消毒では届かない専用の薬剤です。散布し、拭き上げ、再度処理を繰り返しながら、菌の働きを止めていきます。ペットがいた現場では、動物の体液や排泄物が加わり、菌の種類も量も増える傾向があります。
そのため、除菌の工程も慎重に進めなければなりません。この段階を丁寧に行うことで、作業スタッフの安全も守られ、次に続く汚染物の撤去や脱臭の効果が安定します。
汚染物の撤去と害虫駆除
ご遺体の体液が付着した布団や家財、フローリングといった汚れた物を取り除く作業です。同時に、すでに発生しているウジやハエをしっかりと駆除し、臭いの元を一つずつ消していきます。
ペットの遺骸がある場合は汚れの地点が複数に分かれ、撤去する物の量も多くなり、どうしても時間がかかります。体液が床の奥まで入り込んでいることもあり、その場合は表面の素材を剥がし、下にある部分まで処理しなければ臭いは残ります。
この初期判断が正確であるほど、次の工程の効果がしっかり出ます。だからこそ、状況を見極められる業者の力が欠かせません。だからこそ、特殊清掃業者は知識、スキル、ノウハウ、現場経験が求められるのです。
遺品整理と家財の搬出
汚れた部分を取り除いたあとは、部屋に残っている家財や生活用品をすべて外へ出していきます。孤独死の現場では、多くの物が臭いを吸い込んでいて、そのまま残すと後からまた臭気が戻ってくる原因になります。
ペットがいた部屋では、家具の裏や狭い隙間に糞尿が付いていることも多く、ひとつずつ確かめながら進む必要があります。遺族や保証人と相談し、必要な物だけを分け取り、そうでない物は適切に処分します。
この工程を飛ばしてしまうと、後の脱臭作業がうまく機能しません。遺品整理と残置物の撤去は、原状回復に向けて欠かせない土台のようなものです。
本格的な消臭・脱臭作業
汚れの元を取り除いたあとでも、体液や腐敗の臭いは建材の奥に残っています。これを消すには、専用の薬剤を使った処理や、高濃度のオゾンによる脱臭が必要になります。とくにペットの遺骸があった現場では、複数の臭いが混ざり合うため、作業の回数も時間も増えがちです。
脱臭は「密閉」「拡散」「中和」という段階を重ね、臭いを限りなくゼロに近づけていく工程です。ここでの妥協は後々のトラブルにつながり、入居後に異臭が戻ることさえあります。
技術力の差が最も出るのが、この工程です。どこまで丁寧に取り組めるかが、仕上がりを決めていきます。ロードでは「腐敗臭がとれない」といった再施工の依頼をこれまでたくさん受けてきました。同業者からも依頼を受けるほど、ロードでは消臭技術に自信をもっています。
リフォーム・解体工事の必要性判断
消臭が終わったように見えても、床の下や壁の裏、巾木の奥に体液が残っていれば、数週間後に再び臭いが立ち上がることがあります。だからこそ、特殊清掃の業者は解体が必要かどうかを慎重に見極め、汚れがどこまで入り込んでいるのかを確かめます。
場合によっては、フローリングや壁紙だけではなく、その下にある下地材まで交換しなければならないこともあります。ペットが関わった現場では汚れの広がり方が複雑で、解体範囲が広くなる傾向があります。リフォーム費用が大きく変わるのも、そのためです。
だからこそ、「どこまで工事が必要なのか」を正しく判断できる業者を選ぶことが大切です。過剰な工事も、足りない処理も、防ぐことができます。
ロードで実際にあった「ペットの遺骨が見つかった孤独死現場」
孤独死の現場には、外から見ただけでは分からないものが潜んでいることがあります。ロードが対応したある部屋でも、中年の男性が誰にも気づかれず亡くなっていました。
依頼者は弟さん。作業の途中、スタッフが部屋の一角で、小さな遺骨をいくつも見つけました。生前、一緒に暮らしていた犬や猫のものです。部屋には害虫も出ており、特殊清掃と残置物の撤去を進めながら、遺骨は一つずつ確認し、欠片を落とさないように慎重に収集していきました。
作業後、弟さんに状況を説明すると、「供養までお願いしたい」との言葉をいただき、ロードがその役目を引き受けました。8つの遺骨を骨壺に納め、霊園へ運び、共同墓地で読経と納骨を行いました。
オーナーの立場で、ペットの遺骨が見つかるケースはそうめったにあることではないと思いますが、私たちはどんな現場であっても整え、ご家族の心が前へ進めるように寄り添うこと——それが専門業者の大切な役割のひとつと考えています。
この特殊清掃の詳しい内容は下記の実績ページをご覧ください。
埼玉県さいたま市|作業内で発見したペットの猫と犬の供養と共同墓地への埋葬・納骨の実績ページ
「もしものとき」に備えるために——ペットの行き先を決めておく重要性
今回のように、飼い主が亡くなったあとペットがどうなるのか——その話題は、多くの人が触れないまま過ごしてしまうものです。日本では、多くの家庭でペットを飼っていますが、一人暮らしや高齢の世帯では「もしものときの引き取り先」が決まっていないことが少なくありません。
ロードが別のお客さまから聞いた話では、ペット仲間同士で「どちらかに何かあれば、互いのペットを引き取る」と約束している方もいました。家族や兄弟、友人、身近なコミュニティと話をしておくことは、飼い主にとっても、残されるペットにとっても大きな支えになります。
孤独死や物件への影響といった側面だけでなく、身近な命をきちんと守る行動として、早めの準備は大きな意味を持つのではないでしょうか。
まとめ
ペットがいた孤独死の現場は、汚れも臭いも通常より深く残りやすく、復旧までの道のりも複雑になります。だからこそ、最初の対応と、専門業者の力が欠かせません。
適切な順番で進めていけば、部屋は再び募集できる状態に戻せます。オーナーが落ち着いて判断することで、物件への影響も、ご自身の負担も、必要以上に広がらずに済むでしょう。
もしどの業者に依頼して良いか判断に迷うようでしたら、豊富な特殊清掃の実績がある私たちにお気軽にご相談ください。お問い合わせフォームや公式LINE、 もしくはお電話(0120-536-610)の中からご都合の良い方法で、ご連絡いただければと思います。
お問い合わせはこちら
お問い合わせ後に無理な売り込みをすることはありませんので、安心してご依頼ください。
また、どんなささいなことでも気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。