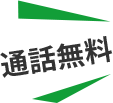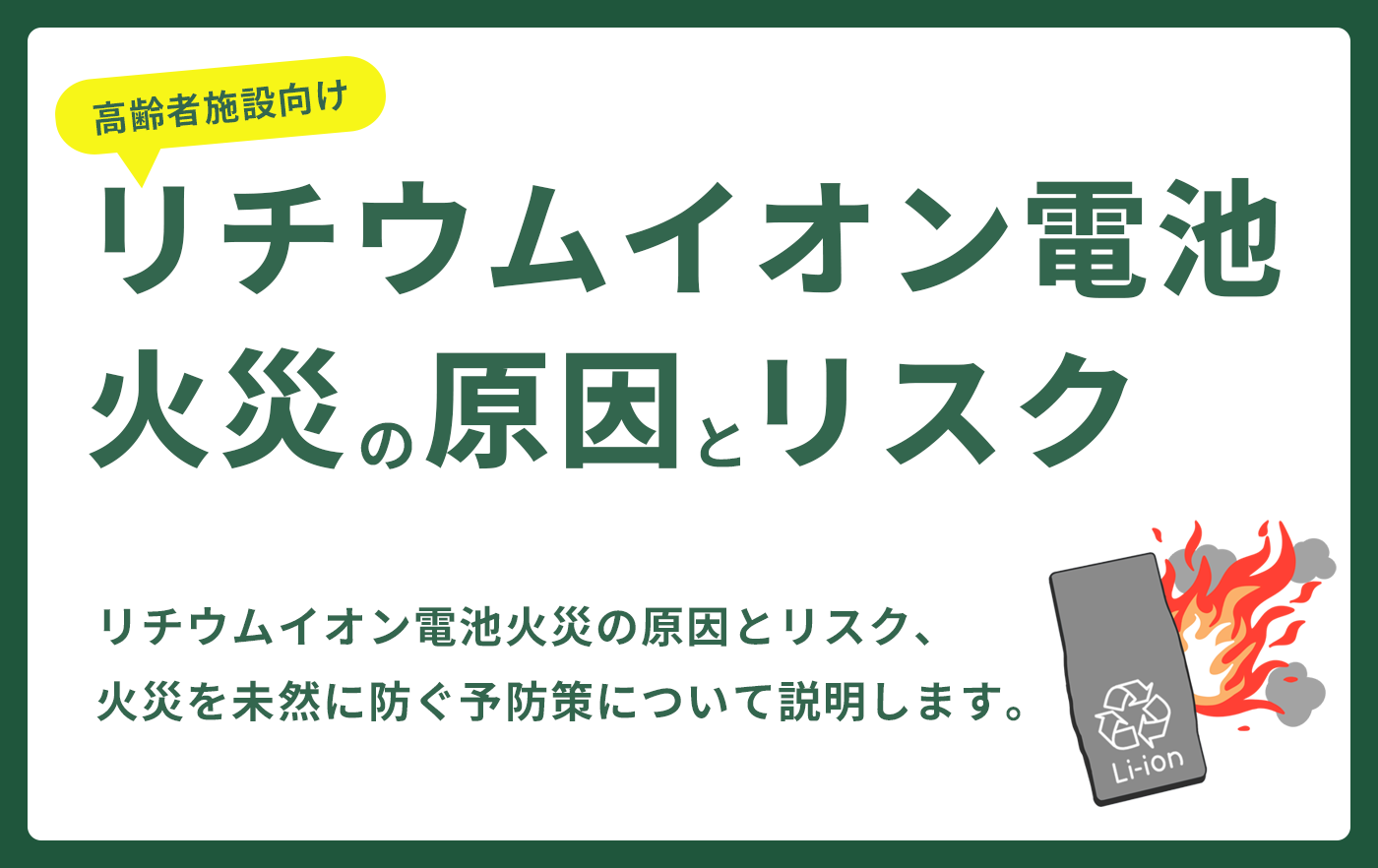
もしも入居者が持ち込んだ電動車いすのバッテリーから発煙したら──その瞬間、どう動くかが施設の信頼を左右します。便利さの象徴であるリチウムイオンバッテリーは、同時に火災リスクの潜む“刃”でもあります。
遺品整理の実績ではありますが、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など福祉施設の対応実績が複数あることから、リチウムイオン電池が要因となる火災のリスクについて、今回は高齢者施設向けにコラムを作成しました。
この記事では介護施設の安全管理責任者が押さえておくべき、リチウムイオンバッテリー火災の原因、そして今日から取り入れられる予防策を、現場感覚で解説します。
目次
全国で増加中!リチウムイオン電池火災のリスク
全国で相次ぐリチウムイオン電池火災──そのリスクは介護施設も例外ではありません。家庭用から産業用まで幅広く使われるこの電池は、電動車いすやコードレス掃除機、加湿器など、施設内のあらゆる機器にも搭載されています。一度でも誤使用や劣化によって発煙・発火が起これば、入居者と職員の命、そして施設の信用を同時に脅かす重大事故になりかねないので、細心の注意が必要です。
電動車いす・コードレス機器に潜む危険
介護施設の現場に当たり前のように存在する電動車いす、コードレス掃除機、電動ベッドなど、その多くに搭載されているのがリチウムイオン電池です。
便利さの裏側で、充電中や長期間の使用後に異常発熱を引き起こすことがあり、とりわけ古いバッテリーや非純正品の利用は、火災リスクを一気に高めます。
過去事例から見る発火原因(短絡・過充電・劣化)
発火事故の背景には、端子同士の接触による「短絡」、必要以上の充電を続ける「過充電」、そして長期使用による「劣化」が三大要因として潜んでいます。
介護の現場ではさらに、落下や衝撃による内部損傷、湿度の高い場所での保管といった日常の小さな出来事が、思わぬ火種となることが可能性として考えられます。
なぜ起こる?リチウムイオンバッテリー火災の原因と構造
リチウムイオン電池は、小さな筐体に大量のエネルギーを蓄えられる高エネルギー密度が魅力ですが、その利便性と引き換えに、誤った使い方をすれば一気に危険へ傾く構造を持っています。
「熱暴走」のメカニズムをわかりやすく解説
熱暴走とは、リチウムイオン電池内部の化学反応が暴走し、発熱が止まらなくなる現象のことです。衝撃、過充電、内部短絡などをきっかけに始まり、一度火がついたように温度が急上昇し、やがて発火や爆発へとつながります。
これを防ぐカギは、日常の適切な充電管理と、落下や圧迫といった物理的ダメージを徹底的に避けることです。
火災防止のための介護施設内管理ポイント
日々の機器管理を徹底することこそ、火災リスクを根本から減らす最も確実な方法です。介護施設では、職員全員が同じ基準と手順で動けるルールを共有し、入居者の持ち込み機器の受け入れから使用・点検・廃棄まで、一貫性のある安全管理体制を築くことが重要なポイントだと考えています。
火災の発生を防止する5つのルール
介護施設でバッテリー火災を防ぐための基本は、下記のようなものが挙げられるかと思います。
- 持ち込み機器の事前確認
- 充電中の常時監視
- 高温多湿を避けた適切な保管
- 寿命を見越した定期交換の推奨
- 正しい廃棄ルートの確保
これらを施設独自のルールとしてマニュアル化し、全職員が迷いなく実行できる状態にしておくことが、火災予防の第一歩となります。
持ち込み機器の事前チェック
入居者が持ち込む機器は、必ず型式・使用年数・メーカーの安全基準を事前に確認し、少しでも異常や不安材料があれば、その場で使用中止や交換を提案します。
特に非純正バッテリーの使用は、火災リスクが高いため厳禁とし、施設ルールとして明確に示すことが重要だと考えます。
使用中・充電中の巡回確認
充電中の機器は、職員が定期的に巡回し、異臭・異音・異常発熱といった危険の兆候がないかを確認することをお勧めします。長時間の放置充電は避け、異常を感じたら即座に使用を中止するようにしましょう。
保管場所の温度・湿度管理
バッテリーは、高温多湿を避けた直射日光の当たらない涼しい場所で保管します。特に夏場や暖房器具の近くは温度上昇が激しく、劣化や発火のリスクを高めるため、避けることが重要です。
古いバッテリーの交換推奨
製造から3〜5年を経過したバッテリーや、充電時間が極端に短くなるなど性能低下が見られるものは速やかに交換します。必要に応じて、施設負担による一括交換を検討するなど、安全性を優先した運用が推奨されます。
廃棄・回収ルートの明確化
廃棄や回収は、自治体やリサイクル協会が定める正式ルートを把握し、それに沿って行います。保管から搬出まで一切の火種を残さないよう徹底することが重要です。
入居者・家族への周知方法
入居者や家族への周知は、火災防止の要です。まず持ち込み機器の受付時に安全説明を行い、使用方法や充電時の注意点を簡潔にまとめたパンフレットなどを渡せればベストです。
施設内の掲示板や共用スペースには写真やイラスト入りの注意喚起ポスターを掲示し、視覚的にも危険性を訴えます。さらに家族会や面会時には口頭で説明する機会を設け、持ち込みバッテリーの定期点検や交換時期についても共有すると良いでしょう。
こうした継続的な情報発信が入居者の安全意識を育て、職員との協力体制を強固にすると私たちは考えています。
もし発煙・発火が起きたら
初期対応マニュアルに沿った行動を行う
万が一、発煙・発火が起きた際は、事前に共有されたマニュアルに沿って、迷いなく迅速かつ正確に行動することが求められます。
発煙や発火を確認したら、即座に周囲の職員へ知らせ、電源を切って充電を中止します。、危険が伴う場合は決して無理をせず避難を優先します。直ちに119番通報を行い、消防到着までの間は可燃物を遠ざけ、安全距離を確保して延焼を防ぎます。
介護施設では何より入居者の安全確保が最優先です。同時に火の拡大を食い止める判断も重要と言えるでしょう。日頃から避難経路や初期消火の手順を全職員が把握し、定期的な訓練で体に染み込ませておくことで、いざという時にも冷静かつ的確な対応ができる可能性が期待できるでしょう。
職員研修に活かせるチェックリストと教材
職員研修は、火災防止の意識と行動基準を全員で共有する絶好の場です。座学で基礎知識を学ぶだけでなく、実際にバッテリーを使った点検手順や発火時の対応を体験することで、緊急時にも迷わず動ける力が身につくでしょう。
この章では、研修で活かせるチェックリストのご案内と、伝えるべき重要ポイントをお伝えします。
バッテリー製品安全管理チェックリスト
チェックリストには、
- バッテリーの外観に膨らみや亀裂がないか
- 充電器が純正品か
- 異音や異臭がないか
- 使用年数
- 保管環境
といった項目を盛り込むとよいでしょう。
点検結果はデジタルまたは紙で記録し、次回点検時に参照できる状態を保ちます。施設内で統一した書式を用いることで、職員間の判断基準を揃え、見落としや対応のバラつきを防ぐことができるでしょう。
研修で伝えるべき5つの重要ポイント
研修で必ず押さえるべき5つのポイントは、
- 過去の火災事例とその原因
- リチウムイオン電池の構造と潜む危険性
- 日常における安全点検の具体的手順
- 発煙・発火時の初期対応
- 入居者や家族への安全説明の重要性
これらは写真や動画、さらには実演を交えて伝えると、職員の理解度を高めることにつながるでしょう。
まとめ
介護施設におけるリチウムイオンバッテリーの管理は、入居者や職員の命、そして施設の信用を守る重要な役割があると言えます。
リチウムイオンバッテリー火災の多くは短絡・過充電・劣化といった基本的な要因から発生し、日常点検や適切な充電・保管で、発生の確率を大幅に下げることができます。
持ち込み機器の事前チェック、古いバッテリーの交換、正しい廃棄、入居者・家族への周知のルール化など、職員全員で徹底することが必要不可欠になるでしょう。
今回の記事が少しでも何かのヒントになれば幸いです。
お問い合わせはこちら
お問い合わせ後に無理な売り込みをすることはありませんので、安心してご依頼ください。
また、どんなささいなことでも気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。