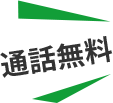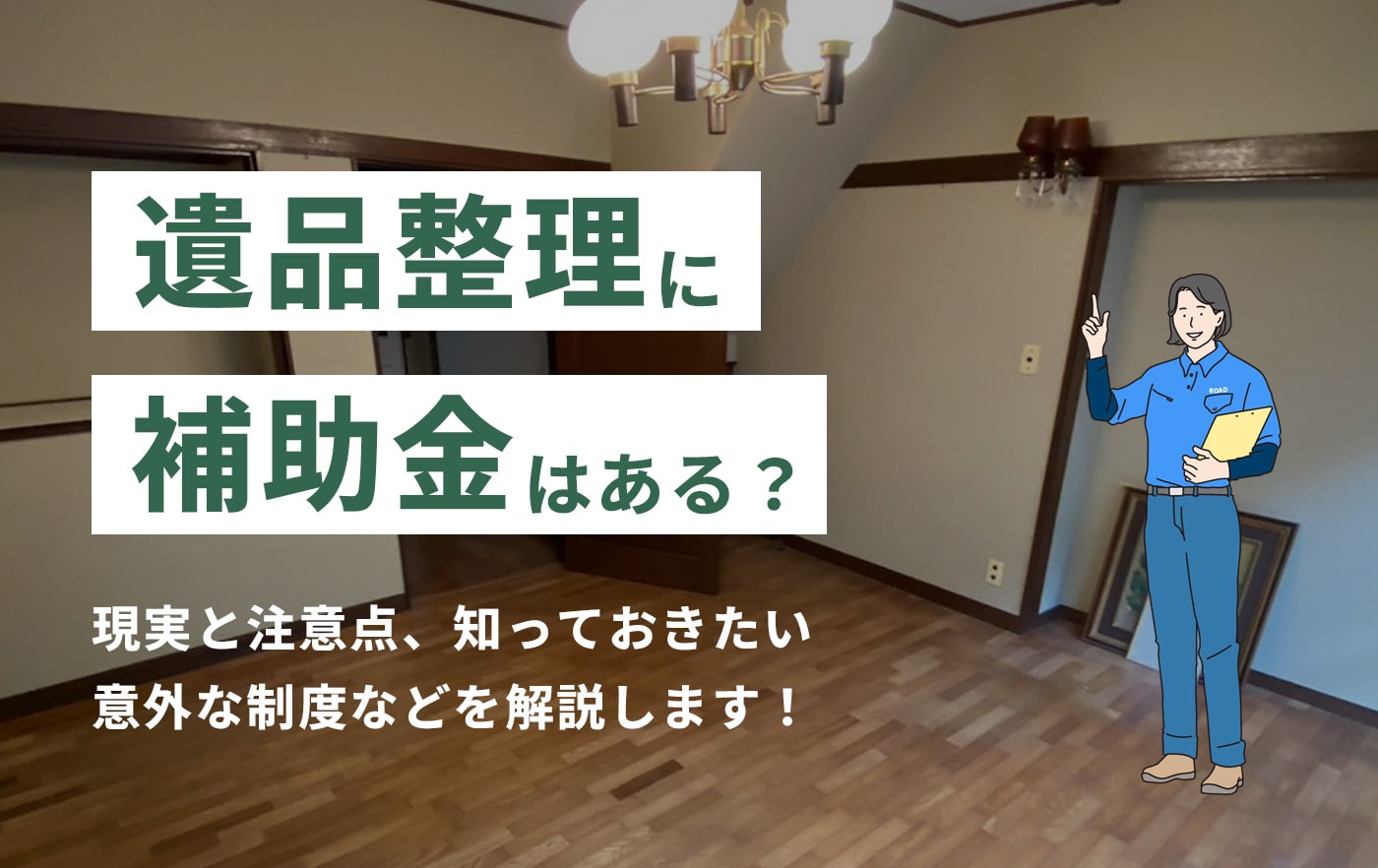
「父が亡くなり、実家の片付けをどうすればいいか分からない…」
遺品整理にかかる費用は、ワンルームでも数万円、戸建てなら数十万円になることもあり、負担の大きさに悩む方は少なくありません。そんなとき、「補助金で費用を軽減できるのでは?」と考える方も多いと思いますが、実際には遺品整理そのものを対象とする補助制度はほとんどありません。
この記事では、遺品整理で補助金が使えるのか、その現実と注意点、さらに知っておきたい意外な制度や費用を抑える方法について、詳しく解説します。
目次
遺品整理に補助金は使えるのか?
国や自治体の遺品整理に対する補助金は「基本的にない」という現実
遺品整理に対する国や自治体の直接的な補助金は、実はほとんど存在しません。
「高齢者支援や災害復興のように、片付け費用を補助してくれる制度があるのでは?」と期待する方もいますが、現実は異なります。
なぜなら遺品整理は基本的に相続人や家族が負担するべき作業とされているからです。一部の自治体では、ゴミ処理費の補助やシルバー人材センターの作業支援があります。ただし、それだけで全額をカバーするのは難しいのが現実です。
遺品整理や特殊清掃などの費用を負担してくれるサービスとは?
補助金ではないですが、見守り・防災サービスの費用補償制度として、遺品整理や特殊清掃の費用を負担してくれるサービスもあります。
例えば北区のホームページでは、見守り・防災サービスの「HelloLight」というサービスを紹介していますが、その中で下記のように記載されています。
[ 対象となるケース ]
利用者が自治体内で自殺、犯罪死、孤独死した場合
[ 支払い対象 ]
利用者の死亡に起因した特殊清掃費用(修繕、清掃、異臭除去、消毒等)、遺品整理
[ 支払額 ]
1事故50万円(税込)が上限
ただし、この制度を利用するには、「HelloLight」への加入(月額利用料が必要)という条件があります。
詳しくは、北区ホームページの東京都北区居住支援協議会会則をご覧ください。
知らなきゃ損!遺品整理と関連する「意外な」補助金や制度
空き家対策補助金
全国的な空き家問題に対応するため、国土交通省の「空家等対策特別措置法」に基づき、全国の多くの自治体が空き家対策を推進するための補助金制度を導入しています。
この制度は空き家の解体や改修費用を補助するものです。たとえば、老朽化した家を取り壊す場合、自治体によっては解体費用に数十万円の補助金を支給する制度があります。
ただし、補助対象は「一定期間空き家であること」「倒壊の恐れがあること」など厳しい条件が多く、遺品整理単体では対象になりません。
遺品整理自体は対象外ですが、空き家の処分を検討している方は、事前に自治体の補助制度を確認しておくことをおすすめします。
高齢者・生活困窮者支援の制度
自治体や社会福祉協議会では、高齢者や低所得世帯向けに「生活支援サービス」を提供しています。
この中には、以下のような支援があります。
- 買い物代行
- 掃除や簡単な片付けのサポート
これらは無料または低額で利用可能な場合があります。
ただし、本格的な遺品整理や特殊清掃は対象外のことが多いので、期待しすぎは禁物です。利用を希望する場合は、役所や地域包括支援センターに早めに相談しましょう。
補助金を利用するための手続きと注意点
申請の基本的な流れ
補助金を利用する場合、基本的な流れは「事前相談 → 見積り取得 → 申請 → 作業実施 → 実績報告」です。ここで重要なのは、申請前に作業を始めないことです。多くの制度では着手前の申請が条件で、事後申請は認められません。
作業を先に始めてしまうと対象外になるケースが非常に多いので注意が必要です。また、見積書や作業計画書を提出する必要があるため、対応できる業者を選ぶこともポイントです。
必要書類の例
補助金の申請には、以下のような書類が求められるケースが一般的です。
- 専門業者の見積書
- 作業前後の写真
- 所有権を確認できる書類(登記簿謄本など)
- 補助金交付申請書
提出書類やフォーマットは自治体によって異なるため、必ず公式サイトや窓口で最新情報を確認しましょう。
写真撮影のタイミングやフォーマットに指定がある場合があります。申請をスムーズに進めるため、事前に準備することが重要です。
よくある落とし穴
先にも触れまたことですが、最大の落とし穴は「作業を先に始めてしまう」ことです。補助金の対象外になる原因の多くは、この事前申請の不備にあります。
また、「対象となる工事や作業の範囲」を誤解しているケースもあります。解体工事が対象になる補助金でも、遺品整理は対象外ということも珍しくありません。さらに、業者が補助金制度に詳しくない場合、書類不備で不交付になることもあるため、業者選びも慎重にすすめることも重要です。
補助金だけで費用はカバーできる?実際の負担イメージ
遺品整理の相場と補助金額のギャップ
遺品整理の費用は、ワンルームで3〜8万円、3LDKで15〜30万円程度が相場です。一方、補助金は数万円程度にとどまるケースがほとんど。
仮に空き家解体補助金を併用できても、解体費用の一部負担に過ぎません。このため、補助金をあてにしすぎると実際の費用が予算と乖離するリスクがあります。まずは自己負担を前提にし、補助金はあくまでサポート程度に考えておくのが現実的です。
補助金を使っても自己負担が必要な理由
補助金は税金で賄われるため、対象範囲や金額は限定的です。遺品整理の全額を補填する制度はほぼ存在せず、解体や福祉支援の一部に限定されることがほとんどです。
また、補助金の申請や実績報告には時間と手間がかかります。そのため「今すぐ整理したい」というニーズには合わない場合もあります。こうした背景から、自己負担は必須であり、補助金はあくまで一部負担の軽減策として利用するのが現実的です。
補助金以外で賢く費用を抑える方法
遺品の買取を活用する
多くの遺品整理業者は、遺品の買取にも対応しています。遺品の中に買い取れるものがあり依頼者も希望すれば、遺品整理の作業費用から買取分の費用を安くできます。
特に、ブランド品や骨董品などは買い取り対象になりやすく、遺品整理費用を大幅に削減できることもあります。
遺品の買取については、別記事「遺品整理時の賢い選択。買取を利用して遺品整理の費用を軽減!」に詳しく書いていますので、気になる方はぜひ合わせてお読みください。
火災保険や損害保険の確認
例えば賃貸物件で孤独死が起きて原状回復のために特殊清掃が必要な場合、火災保険や損害保険で費用をカバーできる場合があります。特に孤独死や事故死などの場合、付帯補償が適用されれば数十万円単位で負担を減らせる可能性がありますので、契約内容を確認することをおすすめします。
まとめ
遺品整理に補助金を直接適用できる制度は、残念ながらほとんどありませんが、私たちも全ての自治体の情報を把握しているわけではありません。
そのため、遺品整理や特殊清掃などの費用に対する補助などは完全にないと言い切れません。孤独死などが社会問題化している今、自治体の対応も変わり、以前はなかった補助が、現在は導入されている場合もありますので、確認することをおすすめします。
一方で、空き家解体補助や福祉に関わることは補助制度を用意している自治体はありますので、火災保険の特約などとうまく組み合わせることで、費用負担を軽減できる可能性があります。
いずれにせよ、補助金を「全額カバーの手段」ではなく、「補助的な支援」と考えることが大切です。事前に情報収集し、制度を早めに確認・相談することが重要です。
もし、「どの遺品整理業者に依頼すればいいか分からない」と迷っているようでしたら、お問い合わせフォームや公式LINE、 もしくはお電話(0120-536-610)の中からご都合の良い方法で、ぜひお気軽に私たちにご相談ください。
お問い合わせはこちら
お問い合わせ後に無理な売り込みをすることはありませんので、安心してご依頼ください。
また、どんなささいなことでも気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。