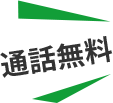賃貸物件で火災起こしてしまい、初期消火を試みるも手に負えず消防を呼ぶ事態に。そして消防の放水により部屋が水浸しになってしまっただけでなく、下の階や隣の部屋にも水が漏れた可能性があると聞いている…
自分の不注意が原因なだけに大きな責任と罪悪感に襲われているが、一方で原状回復費用や損害賠償、仮住まいの費用などお金の面も気になる。
このような心理状態で正しい判断をするのは難しいですが、水浸しになった現場は危険もありますので、もし火災を起こした直後でしたら少しでも冷静になって記事を読み進めていただければと思います。
この記事は賃貸物件で火災を起こしてしまった方向けですが、自宅マンションや戸建ての自宅で火災を起こしてしまった方にも参考になる記事になっています。
目次
火災後、水浸しの現場に入る前に知っておくべきこと
無事、火が鎮火し一見落ち着いたように見える現場も、水浸しの火災現場には新たな危険が発生している可能性があります。室内に入ることはおすすめできませんが、どうしても入らなければならない場合は、自身の安全を最優先するためにも入室前に潜在的なリスクを十分に理解しておきましょう。
漏電・感電の危険がある
火災後の室内は、水濡れによって電気配線や家電にまで影響が及んでいる可能性があり、感電や漏電のリスクがあります。特に床や壁を伝って電気が流れることもあるため、濡れた場所に立ち入るのは非常に危険です。
まずはブレーカーを切って電気を遮断することが基本ですが、落ちているように見えても完全に安全とは限らないため、過信せず慎重に対応しましょう。
ガス漏れの可能性がある
火災による熱や衝撃でガス配管が損傷し、ガス漏れが発生している可能性があります。特に現場では、煙や他の臭気に紛れてガスの臭いに気づきにくいこともあるため、注意が必要です。
やむを得ず室内に入る場合は、決して換気扇を回したり、ライターや電気スイッチに触れたりしないようにし、異臭を感じたらすぐに退避してください。事前にガス会社や消防へ連絡し、元栓の状態や安全確認の有無を確認できればなお良いでしょう。
有毒ガスや汚染物質、カビや細菌の健康被害のリスクがある
火災現場では、有毒ガスや微細な汚染物質が空気中に残留している可能性があり、無色無臭でも吸い込むと健康被害を引き起こす危険があります。例えば、一酸化炭素やダイオキシン類などがその一例です。
さらに、水浸しの状態が続くと、カビや細菌が短期間で繁殖し、アレルギーや呼吸器疾患の原因となることも。特に免疫力の低い人は注意が必要です。入室時はマスク、手袋、長袖、厚底のゴム性長靴などを着用し、必ず防護対策を徹底しましょう。
建物の構造劣化・床抜・天井や壁の崩落の可能性がある
火災後の水浸し現場では、水を吸収した建材が急速に劣化し、床の陥没や天井・壁の崩落といった事故のリスクが高まります。特に木造や築年数の古い建物では、見た目に損傷がなくても内部構造が深刻なダメージを受けている可能性があるため要注意です。
天井のたわみ、壁のひび割れ、異音などにも敏感になり、入室時は複数人での立ち入りや危険箇所への接近を避け、慎重に行動しましょう。
家電やバッテリーの再発火リスク
火災後に水をかぶった家電製品や、リチウムイオンバッテリーを搭載した機器は、内部に水分が残っているとショートや発熱を起こし、再発火のリスクがあります。外見上は無傷に見えても、内部で損傷している可能性が高く、むやみに触れたり通電させたりするのは非常に危険です。
特にリチウムイオンバッテリーは、熱や衝撃、水分によって不安定になりやすく、発火や爆発に至るケースもあります。安全が確認されるまでは、絶対に手を触れず、可能であれば専門業者に状況確認を依頼してください。
火災後、水浸しの現場でまず確認すべきポイント
安全を確保した上で、やむを得ず水浸しの現場に立ち入る際は、次に挙げるポイントを冷静に確認し、記録することが重要です。記録した情報は、後の保険請求や原状回復において不可欠な証拠となります。
まず安全確保をする
ご自身の安全が最優先です。以下の点を確認し、少しでも危険を感じたら無理せず速やかに退避してください。
ブレーカーを落とし漏電・感電のリスクを下げる
入室前には必ず建物のメインブレーカーをオフにして、主電源を遮断しましょう。濡れた配線やコンセントは通電していると感電のリスクが非常に高く、通電状態のまま入室することは絶対に避けるべきです。
ブレーカーをオフにしても100%電気が遮断されているとは限りませんので頭に入れておきましょう。例えば火災の影響で電気設備が破損していると、ブレーカーがオフになり見た目は遮断されたように見えても実際には落ちていないケース、電気配線や家電がショートし、壁や床の中に漏電状態が残っているケースなどもあるため細心の注意が必要です。
安全が確認されるまでは長靴やゴム底の厚い靴を履き、絶対に素足で濡れた床に入らないようにしましょう。
チェックできる範囲で床・壁・天井の水染みを確認する
目視できる範囲で、床の浮きや壁・天井の水染み、たわみ、ひび割れなどを確認しましょう。これらは建物の構造が損傷しているサインであり、特に天井裏や壁の内部は目に見えないダメージが進行している可能性があります。
少しでも異変を感じたら無理に動かず、速やかに退避し専門家の判断を仰いでください。
異臭・ガス臭の有無を確認する
入室直後に焦げ臭や化学薬品のような異臭、卵の腐ったような硫黄臭、またはガス臭を感じたら、すぐに現場から離れて関係機関に連絡しましょう。
有毒ガスやガス漏れの可能性があるため、換気扇を回すなどの行為は避け、体調に異変を感じた場合は無理せず屋外で呼吸を整えることが大切です。安全確認がされるまでは、自己判断での再入室は絶対に控えてください。
被害状況を記録(証拠保全)する
安全が確認できたら、被害状況の記録を開始します。これは保険会社への請求や、大家さん・管理会社との今後のやり取りにおいて、客観的な証拠となります。
水位線が分かるように広範囲から写真を撮る
水浸しの被害を正確に伝えるため、壁や家具に残る水位線を含めて部屋全体を広角で写真や動画に記録しましょう。部屋の四隅から撮影し、水の浸入範囲や家具の下に溜まった水など細部も撮影することが重要です。
時間が経つと水位線が見えにくくなるため、できるだけ早い段階で証拠を残し、保険申請や業者とのやり取りに役立てましょう。
家財や持ち物の被害状況を確認する
通帳や保険証券、身分証明書、契約書など重要書類は最優先で探し、見つけたら安全な場所に保管してください。ただし、危険を冒してまで探す必要はありません。
その他、水浸しで被害を受けた家電や家具、衣類、本などの所有物は、一つひとつ丁寧に確認し、写真や動画で記録しましょう。特に家電は型番や購入時期が分かるように撮影し、家具や衣類は損傷の程度が分かるように残すと損害算定に役立つ可能性が高まります。
下の階や隣室への浸水の可能性を確認する
自身の部屋だけでなく、下の階や隣室に水漏れしているかどうか、外から見える範囲で、また共用部を見ながら確認・推測しておくと良いでしょう。管理会社や大家さんに連絡し、状況確認するのも良いでしょう。
放水で水浸しの火災現場で発生しやすい二次被害とは?
火災の直接的な被害だけでなく、消火活動による放水が原因で発生する「二次被害」があることを理解しておきましょう。
家電製品のショートや故障による感電
すでに何度か触れたように、水濡れした家電製品はショートや故障、感電や再発火のリスクが高いため、乾燥後も自己判断での使用は避け、必ず専門家やメーカーに相談してください。
無理に修理や乾燥を試みることは危険です。家具も内部に水分が残ると変形やカビが発生しやすく、修復が難しくなります。見た目が乾いていても内部の乾燥は難しいため、必要に応じて処分を検討し、安易に室内に放置しないことが大切です。
悪臭やカビ・害虫の発生
火災後の放水で湿気を帯びた建材や布製品は、強い悪臭の原因となり、数日でカビや腐食が進行します。これにより建物の資産価値が損なわれるだけでなく、アレルギーや呼吸器疾患など健康被害のリスクも高まります。
さらに、高湿度環境はハエをはじめとする害虫の繁殖を助長し、生活環境の悪化や近隣トラブルに発展する恐れもあるので注意が必要です。
建物構造材の腐食
消火水が柱や梁、床材といった建物の構造材に浸透すると、木材は水分を吸収して強度が著しく低下し、耐久性が損なわれます。特に木造建築ではシロアリの被害や腐朽菌の発生リスクも高まり、放置すると大規模修繕や建替えが必要になる可能性があります。
水浸しの火災現場の復旧は専門業者に任せるべき
火災後の水浸し現場の復旧作業は、単なる片付けや乾燥作業ではありません。見えない危険や専門的な知識が求められますし、スピードが求められます。
水抜き・乾燥・消臭は一刻を争う
水浸しの部屋は一刻も早く水を除去し、徹底的に乾燥させる必要があります。時間が経つほどカビの発生や建材の腐食、悪臭の定着が進み、修復が難しくなります。
家庭用の乾燥機器では床下や壁内に残る水分を完全に除去できないため、専用機材と技術を持つ専門業者による迅速な対応が不可欠です。業者の強力な送風機や除湿機、特殊洗浄剤による処置が、二次被害を最小限に抑える鍵となります。
なぜ業者に任せるべきなのか?
水浸しの現場はさまざまなリスクがありますが、専門業者は有毒物質の除去や正確な判断、カビや悪臭の根本的な除去、アスベストなどの危険物質処理に豊富な知識と経験を持ち合わせていることが任せるべき大きな理由です。
また、自分で片付けを試みると、被害の拡大や保険適用外となる可能性があることも忘れてはなりません。
専門家に任せることで負担が軽減され、精神的にも安心して復旧作業を進められます。健康被害の防止と建物の長期的な保全のため、復旧は必ず専門業者に依頼しましょう。
火災を起こしてしまった場合、どこに相談すべき?
まずやらなければならないのは、何より消火が最優先なので消防署ですが、ここでは鎮火後を想定して話を進めます。
大家さん・管理会社へ連絡する
まず、最も身近で重要な相談相手は大家さんや管理会社です。物件の所有者として、建物の修復や他の入居者への影響について、入居者と協力して対応を進める必要があります。
そのため、まずは正確な状況報告が何より重要です。その後について指示を仰ぎ、指示に従って行動することで、不必要なトラブルを避けることができます。また、彼らが提携している修繕業者や保険会社がある場合もあるため、初期段階での連携が非常に重要です。
火災保険会社に連絡し請求手続きを行う
賃貸物件の場合、入居時に火災保険へ加入していることがほとんどです。多くの場合は管理会社や大家さんが指定する保険に加入しており、保険会社の連絡先を自分で把握していないこともあります。
もし直接保険会社や契約している保険の内容がわからない場合、まずは管理会社または大家さんに保険の詳細を確認し、加入している保険会社への連絡・手続きを進めましょう。保険金請求には、被害状況の記録や必要書類の準備、鑑定人の立ち会いなど、いくつかの手順が必要です。不明な点は、遠慮なく保険会社や管理会社に問い合わせることが大切です。
まとめ
火災後の水浸し現場には、漏電や有毒ガス、建物の構造劣化、カビの繁殖など多くの見えない危険が潜んでいます。安易な立ち入りは避け、安全確認を最優先にし、やむを得ず入室する際はこの記事のチェックポイントを参考に十分安全に留意するようにしてください。
水位線や家財の被害状況を詳細に記録することが、保険請求や原状回復の重要な証拠となります。また、二次被害の進行を防ぐには、専門業者による迅速な水抜き・乾燥・消臭が必要です。一人で抱え込まずに、管理会社や保険会社、必要に応じて専門家の支援を得て、冷静に対処しましょう。
もし火災現場の復旧作業について、どの業者に依頼すれば良いかわからないようでしたら、お問い合わせフォームや公式LINE、 もしくはお電話(0120-536-610)の中からご都合の良い方法で、ぜひお気軽に私たちにご相談ください。
火災現場の詳細ページもご用意していますので、ぜひそちらもご覧ください。
火災現場のサービス詳細ページはこちら
お問い合わせはこちら
お問い合わせ後に無理な売り込みをすることはありませんので、安心してご依頼ください。
また、どんなささいなことでも気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。